| 今週のおすすめ〔25〕 |
◇吉村公三郎の友情映画『暖流』 (2008/05/24)  ◇またしても映画の話です。前回に続いて戦前の日本映画です。戦前とは言っても昭和14年、つまり日華事変の真っ最中ですから、戦前と言えるどうかは微妙です。事変は戦争に非ずというのは当時の日本政府の立場ですが、それは常識のレベルでは詭弁ですからね。そうすると、戦前とは昭和16年12月8日より前のことなのか、それとも昭和12年7月7日より前のことなのかという問題になりますが、それはここでは措くことにします。また、今回取り上げる映画も当店の在庫にはありません。ご了承ください。 ◇またしても映画の話です。前回に続いて戦前の日本映画です。戦前とは言っても昭和14年、つまり日華事変の真っ最中ですから、戦前と言えるどうかは微妙です。事変は戦争に非ずというのは当時の日本政府の立場ですが、それは常識のレベルでは詭弁ですからね。そうすると、戦前とは昭和16年12月8日より前のことなのか、それとも昭和12年7月7日より前のことなのかという問題になりますが、それはここでは措くことにします。また、今回取り上げる映画も当店の在庫にはありません。ご了承ください。◇今回取り上げるのは、昭和14年12月1日に公開された吉村公三郎監督の映画『暖流』です。出演者は、佐分利信、高峰三枝子、水戸光子、徳大寺伸など。小林信彦はこの映画について次のように述べています。「三時間の映画を二時間に縮めた版が残るだけだが、それでもまず話が面白い。フランス映画のような場面もある。技巧派、吉村公三郎の戦前の代表作。」(『ぼくが選んだ洋画・邦画ベスト200』文春文庫) ◇また双葉十三郎は次のように述べています。「ひと口でいえば恋愛メロドラマであるが、吉村監督はいい意味で気取った演出タッチで映像的に魅力のある場面をくりひろげ、前後編併せて三時間弱(・・・現存しているのは前後編を併せた124分の再編集版)を飽きさせなかった。出演者の扱い方のうまさも成功の要因だが、特に水戸光子は今日でも石渡ぎんという役名が思い浮かべられるくらいの好演だった。」(『日本映画ぼくの300本』文春新書) ◇そうなのです。水戸光子が絶品なのです。昭和49年にルバング島から帰還した小野田寛郎少尉は、結婚したい女性のタイプはと聞かれて、「水戸光子みたいな人」と答えたそうです。ジャングルの小野田少尉を30年にわたって支え続けたのが、かつて映画館で見た水戸光子の面影であったとすると、女優としては最高の勲章と言うほかありません。この映画を見れば、小野田少尉の答えがひいき目でもなんでもないことが理解されるはずです。それほど看護婦・石渡ぎんを演ずる水戸光子は素晴らしい印象を残します。 ◇ところでこの映画はまだDVD化されておりませんから、VHSで見ました。ですから字幕はありません。しかし字幕は不可欠と言いたいぐらい音声がよくない。セリフが聞き取れないところも少なくありません。画質も貧弱です。しかしそうであるがゆえに構想力が触発されます。それによって映画を補完し構成していくという見方が生まれてきます。公開当時のフィルムがどうであったかは知りませんが、そういう無意識の作業を通じて若き小野田少尉の目でこの映画を見ているような気がしてきます。これが古い映画のいいところです。もちろんよくできた映画でなくては、構想力が触発されるということもありませんが。 ◇この映画の最も美しい場面のひとつは、大病院のオーナー兼院長の令嬢・志摩啓子(高峰三枝子)と、看護婦・石渡ぎん(水戸光子)が話をするニコライ堂が見える喫茶店の場面です。そこで啓子は、病院の主事・日疋祐三(佐分利信)へのぎんの愛を知って身を引くことを決断します。そこで交わされるのは次のような会話です。啓子「ね、任せて。あなたもおっしゃい。わたくしからも言いますわ」、ぎん「だって。いいんですの?そんなことしていただいて」、啓子「どうして?」、ぎん「なんだか、悪いような気がして」、啓子「誰に?」、ぎん「もしかして、あの方に。それから、あなたに」、啓子(うろたえて)「そんなこと、そんなこと、ありませんわ。」 ◇この映画は一見すると、日疋祐三、志摩啓子、石渡ぎんのあいだに展開する三角関係のメロドラマに見えます。しかし上の会話に見られるように、実際は友情のドラマなのです。この映画の最後で結ばれるのは日疋とぎんですが、日疋は啓子に結婚を断わられた敗者です。ぎんにしても、自分のために身を引いた啓子への罪の意識から逃れられません。啓子は日疋を納得させる言葉を語って身を引くのですが、自らの潔さと日疋を失った喪失感のあいだで引き裂かれたままです。しかし、三人が敗者になることで何かが勝利したことが分かります。それは友情とも連帯とも言いうる"個を超えた何か"です。実際この映画は強い高揚感とともに終わります。この非常時感覚ゼロに見える映画が大ヒットした理由はそこにあるのかもしれません。 ◇『暖流』の非常時感覚のなさは、画面に出てくるのが、私立の大病院、鎌倉山の別荘、本郷の洋館、外国製の乗用車、上流令嬢の衣装、白いピアノ、ざあます言葉、などであることからも理解されます。院長の長男・志摩泰彦(斎藤達雄)は「ドライブとダンスとゴルフ」しか興味がない人物として描かれますし、啓子に野心を抱く若い医師・笹島(徳大寺伸)はぎんによって「キザで、少し高慢で」と評されるような人物です。極めつけは高峰三枝子演ずる上流階級令嬢・志摩啓子の衣装、言葉、しぐさです。しかしそうした外見にもかかわらず、彼女は倫理的で潔い女性であることが分かってきます。そうした啓子の倫理的な一面は、のちに吉村公三郎がつくる映画『夜の河』(昭和31年)のヒロイン舟木きわ(山本富士子)にも見られます。 ◇先にニコライ堂が見える喫茶店の場面について述べましたが、ニコライ堂が見える喫茶店の場面といえば、小津安二郎の映画『麦秋』(昭和26年)を思い出さないわけにはいきません。そこにおいて志摩啓子が重大な決定をするように、『麦秋』では原節子演ずる紀子に決定的なものが現われます。また、佐分利信演ずる日疋祐三の吸うタバコが彼の階級を表わすのですが、それは小津の『お茶漬の味』(昭和27年)に引き継がれているようです。後者で同じような野人的キャラクターを演ずるのも佐分利信です。 ◇もっと言いますと、『暖流』は志摩啓子が鵠沼海岸(物語上は三保の海岸とされているようですが、富士山が見える方向からして相模湾沿いの海岸であることは明らかです。ここでは鵠沼としておきます)を走っていく場面で終わりますが、小津の『戸田家の兄妹』(昭和16年)は、佐分利信演ずる昌二郎が鵠沼海岸を走って逃げる場面で終わります。誰から逃げるのかというと、今度は妹を演じている高峰三枝子と、その親友役の桑野通子からです。映画全体のトーン、水戸光子を除く主要な俳優が同じであること、どちらも池田忠雄が脚本を書いていることなどからして、この映画は『戸田家の兄妹』の姉妹編という印象が濃厚です。これらについてはこれまで誰も述べていないようなので、指摘だけしておきます。 ◇この映画は友情映画であるともに階級映画でもあります。この映画がメロドラマを超えた人間(=人と人の間)のドラマになっているにもかかわらず、メロドラマの枠組が残るのは、そのことにかかわっています。それは次のような啓子のセリフで語られます。「わたくしね、今だから申しますけど、笹島さんなんて方よりあなた(日疋)の方がずっと好きでしたわ。ただ、どういうものか酔えなかったんです。酔うなんて、変な言葉ですけど。でも、好きには好きですわ。好きなくせに、これが宿命っていうのか」。これがこの映画のメロドラマ的枠組であり、階級映画的枠組です。つまり、友情は階級を超えるが、恋情は階級を超ええないということ。しかし、人間にとって恋を失うことは、実はそれほど重大なことではないということ。人間にとって致命的なことは、友情、尊敬、思いやり、誇りを失うことであるということ。この『暖流』という映画が語っているのはそういうことです。そして、そのことを私たちに伝えているのが志摩啓子を演ずる当時21歳の高峰三枝子なのです。 |
| 今週のおすすめ〔24〕 |
◇清水宏の映画『有りがたうさん』など (2008/05/19) 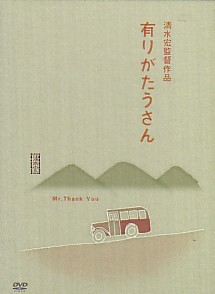 ◇今回も映画の話です。それも古い日本映画の話です。古いとは言っても、それはつくられた年代のことであって、映画の中味が古いという意味ではありません。それどころか、「古くならないものが新しい」という小津映画のセリフに従うなら、むしろそれは新しい。そういう映画の話ですが、今回も当店の在庫にはありません。ご了承ください。 ◇今回も映画の話です。それも古い日本映画の話です。古いとは言っても、それはつくられた年代のことであって、映画の中味が古いという意味ではありません。それどころか、「古くならないものが新しい」という小津映画のセリフに従うなら、むしろそれは新しい。そういう映画の話ですが、今回も当店の在庫にはありません。ご了承ください。◇今回取り上げるのは、ようやくDVD化され始めた清水宏(1903〜66)の映画です。小津映画の常連俳優でもあった笠智衆が、「最近は、小津作品の評判がますます高いが、清水監督にも、すぐれた作品が何本もあると思う。だれも清水作品のことを言わないのが不思議だ」(『俳優になろうか』朝日文庫)と述べていた清水宏の映画です。 ◇笠智衆が上のように述べたのは20年以上前のことで、いまでは佐藤忠男以下の映画研究者たちはもとより、小林信彦、川本三郎、中野翠といった人たちもあちこちで言及していますから、「だれも清水作品のことを言わない」状況はもう過去のものになっています。それどころか、いまや清水宏の代表作のひとつ『按摩と女』(1939)のリメイク版が、SMAPの草薙剛主演でつくられるような時代です(石井克人監督『山のあなた〜徳市の恋』)。 ◇そうすると清水宏は、溝口、小津、黒澤、成瀬と並ぶ巨匠として認知されているのかというと、そういうことではないようです。ここに挙げた4人につぐ巨匠ということでは、山中貞雄の方が「先」でしょう。この「先」か「後」かということは、清水宏の映画を考える場合、意外に重要な意味を持ってきそうです。というのは、清水宏の映画がもたらす感動は、山中を含む他の作家たちのそれとは質が違うように思われるからです。 ◇それでは映画に即して見ていくことにします。まず、小林信彦(『ぼくが選んだ洋画・邦画ベスト200』文春文庫)、双葉十三郎(『日本映画ぼくの300本』文春新書)、佐藤忠男(『日本映画300』朝日文庫)が揃って取り上げている1936年の映画『有りがたうさん』からいきます。 ◇この映画について小林信彦は「ロードムーヴィーの秀作。伊豆を走るバスの運転手が上原謙だが、道路工事に動員された朝鮮人労働者の群れを描いたシーンに胸をつかれる」と述べ、双葉十三郎は「清水宏監督は風景を描くことが好きで巧みだった。この作品もオール・ロケで、スクリーン・プロセスさえも使わなかった。ちょっと皮肉な人生模様が、長屋や都会生活ではなく、自然のなかで展開されるという手法が斬新で、のびのびしたムードに人間味が溶け込み、いかにも清水宏の世界が広がっていた。五所平之助監督の『伊豆の踊子』(33)を意識しながら、それとは別の伊豆を描いてみせた」と述べています。 ◇さすがに双葉十三郎は的確な指摘をしています。というのは、「ちょっと皮肉な人生模様が、長屋や都会生活ではなく、自然のなかで展開される」という指摘は、『有りがたうさん』の少しあとにつくられた『按摩と女』(38)や『簪(かんざし)』(41)にもほぼ当てはまるからです。双葉十三郎が言っているように、「清水宏監督は風景を描くことが好きで巧みだった」ようです。そういうこともあって、清水宏の映画に登場する人間たちは、旅人、流れ者、移動する者たちが中心になることが多いようです。 ◇『有りがたうさん』に戻りますと、この映画の物語は、有りがたうさんと呼ばれる下田と修善寺(あるいは三島か?)を結ぶバスの運転手(上原謙)を中心にして、バスに乗り合わせた黒えりの女(桑野通子)、東京へ売られていく娘(築地まゆみ)、その母親(二葉かほる)、怪しげな髭の紳士(石山隆嗣)といった人物たちをめぐって展開されます。しかし人物たちと並んで、あるいはそれ以上に私たちを捉えるのが、バスが走る街道周辺の風景です。昔の映画ですからもちろんモノクロですが、陽光を受けた野山の緑、空の青さ、雲の白い感じが実に鮮やかに捉えられ、カラー映画よりもっとリアルで深い自然の色が見えるようです。 ◇この映画の山は、チマチョゴリを着た朝鮮人労働者の娘(久原良子)と有りがたうさんの交流の場面であると言えます。彼女は道路工事に動員された朝鮮人労働者の娘で、仲間たちとともに信州のトンネル工事現場へ向かっているところです。彼女はバスの脇で有りがたうさんに向かって次のように言います。「あたし、あそこの道ができたら、一度日本の着物を着て、ありがとうさんの自動車に乗って通ってみたかったわ。でもあたしたち、自分でこしらえた道、一度も歩かずに、また道のない山へ行って、道をこしらえるんだわ」。 ◇これに対して有りがたうさんは次のように言います。「駅までこれに乗ってったら?送ってやるよ」。しかし娘は答えます。「みんなと一緒に歩くの、みんなと一緒に」。そのあと峠道を歩く朝鮮人労働者の群れを捉えたロングショットに切り替わります。これが小林信彦が「胸をつかれる」と述べているショットですが、もっと胸をつかれるのはそれに続く場面です。娘と有りがたうさんは「さよなら」と言い合って別れるのですが、有りがたうさんの運転するバスが前方のトンネルに向かって長いクラクションを鳴らします。そのクラクションの響きが朝鮮の娘と有りがたうさんの言葉にならない慟哭のように聞こえるのです。 ◇こうしてこの映画は終盤に向かっていきます。最後に有りがたうさんが行うことは、東京に売られていく日本人の娘を救うことです。それを後押しするのがバスに乗り合わせた黒えりの女(桑野通子)で、彼女は次のように言います。「シボレーのセコハン買ったと思や、あの娘さんは一山いくらの女にならずに済むんだよ」。有りがたうさんは朝鮮の娘に対しては、死んだ彼女の父親の墓に水をやり花を供えることを約束する以上のことができませんでした。それをそういう形でいわば埋め合わせるのですが、それでいいのです。日本においてできることを行うこと。労働者国際主義にしても、そこからしか生まれてこないのですから。ちなみに「シボレーのセコハン」とは、有りがたうさんが独立するために買うつもりでいた自動車のことです。 ◇1938年の『按摩と女』は、山の中の温泉場における按摩(徳大寺伸)と東京からきた謎めいた女(高峰三枝子)の恋物語です。小林信彦は「なんということもない話のようで、ラストの馬車を送るショットに心がふるえる」と述べています。この「なんということもない話のようで」というのが重要なポイントですが、それは清水宏の映画が自然の風景のなかを流れ去っていくように展開することからきています。『有りがたうさん』の桑野通子の役は流れ者の水商売女ですが、『按摩と女』の高峰三枝子の役は東京の旦那のところから逃げてきた妾で、旅人、流れ者という共通点をもっています。徳大寺伸が演ずる按摩にしても温泉場を渡り歩く流れ者です。 ◇ですから恋物語と言っても、それは流れ去っていく恋、すれ違っていく恋でしかありません。そういう無常のなかに永遠を見るというのが清水宏のドラマの特徴であるようです。それはメタ日常的な時間のドラマであるとも言えるかもしれません。そういう作風が関係していると思われますが、この映画の高峰三枝子は圧倒的に美しい。中野翠も「私はこの映画で、高峰三枝子の冴え冴えとした不思議な美貌に心打たれたのだ」と述べています(『会いたかった人、曲者天国』文春文庫)。中野翠は同じ本のなかで『有りがたうさん』の桑野通子については、「黒えりの着物姿の美しい流れ者」と述べていますが、高峰三枝子にせよ桑野通子にせよ、同時期の小津映画に見られるよりも更に魅力的でさえあります。 ◇とりわけ高峰三枝子が演じるヒロインの驕慢すれすれの気品と佇まいは、ほとんど衝撃的と言いたいほどです。「ドラマの本質は人格をつくり上げることだと思う」と語ったのは小津安二郎ですが、その人間がもっている芯のようなものを瞬時につかむということでは清水宏の方が上だったようです。つまり清水宏の映画に比べると、韻文的な小津映画でさえ散文的に見える。流れ去っていく風景のような清水宏の映画においては、ドラマの骨格が前景化されていない分、各ショットの独立性が高いということでしょう。 ◇とにかく昭和10年代の日本映画は素晴らしい。『浪華悲歌』(溝口、1936)、『淑女は何を忘れたか』(小津、1937)、『人情紙風船』(山中、1937)、『残菊物語』(溝口、1939)と並べただけで、その時代が日本映画の黄金時代であったことが分かりますが、『有りがたうさん』にせよ、『按摩と女』にせよ、『簪』にせよ、ある意味ではそれらを凌いでさえいます。機会があったらぜひご覧になってください。 [追記:つい最近『山のあなた〜徳市の恋 ガイドブック』という本(ぴあMOOK)が出ました。オリジナルの『按摩と女』や清水宏を紹介する文章もちゃんと収録されています。興味がありましたら新刊書店でご覧ください。そして映画も見ましょう。よろしかったらオリジナルも。(2008/05/21)] |
| 新着ガイド〔今週のおすすめ/番外〕 |
◇北一輝、吉本隆明、フロイト、カール・シュミット、など (2008/05/12)  ◇ひさしぶりに古書がまとまって新着なりました。それも、なんとなく1970年前後にタイムスリップしたようなラインナップです。吉本隆明、橋川文三、桶谷秀昭、磯田光一、内村剛介、三島由紀夫、高橋和巳、見田宗介(真木悠介)、埴谷雄高、森秀人、柳田國男、それに北一輝。フロイト、カール・シュミット、魯迅、レヴィ=ストロースなどもありますが、総じて全共闘的気分が濃厚な名著のオンパレードです。 ◇ひさしぶりに古書がまとまって新着なりました。それも、なんとなく1970年前後にタイムスリップしたようなラインナップです。吉本隆明、橋川文三、桶谷秀昭、磯田光一、内村剛介、三島由紀夫、高橋和巳、見田宗介(真木悠介)、埴谷雄高、森秀人、柳田國男、それに北一輝。フロイト、カール・シュミット、魯迅、レヴィ=ストロースなどもありますが、総じて全共闘的気分が濃厚な名著のオンパレードです。◇なかには高橋允昭『デリダの思想圏』、リチャード・セネット『公共性の喪失』、内田樹『死と身体』といった比較的最近の本もあります。本の状態は古いものほど函ヤケ、背ヤケが目立ちますが、本文、本体について言えば、概して良好と言えます。詳細は備考欄をご覧ください。また、それぞれの価格はベストプライスと言えると思います。 ◇今回入荷した古書の大まかな傾向についてコメントさせてもらいますと、大澤真幸の言う「理想の時代」の後半、即ち見田宗介の言う「夢の時代」、つまり1960〜75年頃の思潮の核心が概観できるラインナップと言えます。言い換えれば、「理想の時代」前半の中心的思潮であった未来志向型民主主義、社会主義、マルクス主義といった「大きな物語」を、伝統的なもの、土着(情念)的なものの方から捉え返して行こうという傾向のものが多いこと。北一輝、保田與重郎(日本浪漫派)、柳田國男などはそういう方向からその時期に盛んに読まれました。 ◇それが日本における近代的思潮の終焉、即ちポスト近代的な思潮へと転回して行く際の際立った特徴であったと言えるでしょう。そういうこともあって、その時期の思想書には様々な要素が混在していますし、また入り組んでもいます。橋川文三の本が「哲学/思想」、「文芸」、「政治」の3箇所に分類されているのはそういう事情によっております。吉本隆明もそういう風に分けるのがいいのでしょうが、『西行』も『吉本隆明新詩集』もまとめて「哲学/思想」に分類しております。ご了承ください。また、今回民俗学関係の本がまとまって入荷しましたので、新たに「民俗」というジャンルを設けることにしました。 ◇それからカール・シュミットは「哲学/思想」に分類すべきか、「政治」に分類すべきか迷いましたが、これは「政治」の方に入れました。カール・マンハイムも「社会」か「哲学/思想」か迷いましたが、同じ理由で「社会」に分類しました。レヴィ=ストロースは「哲学/思想」より「民俗」の方にはるかに近いはずですが、これは普通の書店の分類に従って「哲学/思想」に入れました。北一輝を「政治」ではなく「哲学/思想」に分類したのは、政治思想の「思想」の方に重点を置いた方がよさそうだという判断によっています。 ◇「おすすめ」ということでは、上に述べたような意味で日本がポスト近代へと転回して行く際のマイルストーン的著作が並んでいますから、どれもおすすめと言いたいころですが、まずは全3巻揃った『北一輝著作集』(みすず書房)をおすすめします。私自身は読んでいないのですが、革命思想の日本型ディコンストラクションの書としても読まれうるかもしれません。あとはやっぱり世界最大のポストモダニスト吉本隆明の『著作集』(勁草書房)1〜14+(続)10巻、それから定番中の定番『フロイト著作集』(人文書院)1〜8巻、そして入手が難しそうなカール・シュミットの『リヴァイアサン』(福村出版)と『陸と海と』(同)などなど。 ◇ほかにもまだどっさりあります。橋川文三、磯田光一、桶谷秀昭、魯迅、三島由紀夫などもお買い得のはずです。大東亜戦争関係なども。どうぞごゆるりとご閲覧ください。 |
| 新着ガイド〔今週のおすすめ/番外〕 |
◇天地真理、ユーミン、サザン、藤圭子、等々 (2008/05/05)  ◇日本のポップス(J-Pop)の中古CD44点、演歌/歌謡曲の中古CD29点、その他邦楽中古CD12点、合計85点が新着なりました。もう少し詳しく言うと、グループ・サウンズ、天地真理、ユーミン、サザン、藤圭子、門倉有希、李香蘭から、軍歌/戦時歌謡まで。内容的には最近アップしたクラシック、ジャズにも勝るとも劣らないキラーなラインナップです。前置きはこれぐらいにして少しコメントさせていただきます。 ◇日本のポップス(J-Pop)の中古CD44点、演歌/歌謡曲の中古CD29点、その他邦楽中古CD12点、合計85点が新着なりました。もう少し詳しく言うと、グループ・サウンズ、天地真理、ユーミン、サザン、藤圭子、門倉有希、李香蘭から、軍歌/戦時歌謡まで。内容的には最近アップしたクラシック、ジャズにも勝るとも劣らないキラーなラインナップです。前置きはこれぐらいにして少しコメントさせていただきます。◇天地真理から行きます。当リストにある『ザ・ベスト』は、「水色の恋」、「ちいさな恋」、「ひとりじゃないの」、「恋する夏の日」以下の大ヒット曲を網羅した必聴必携盤です。天地真理が「水色の恋」で鮮烈なデビューを飾ったのは1971年10月です。その時期は、大澤真幸『不可能性の時代』(岩波新書)の時代区分に従うと「理想の時代」から「虚構の時代」への移行期に当たるわけですが、歌詞も曲も完璧なファンタジーと言えます。なにしろ「白雪姫みたいな心しかない私」ですから。 ◇「我々は、天地真理の人生の最も輝いている一時期を消費し尽くした。その責任を取らねばなるまい」という言葉(金子修介『失われた歌謡曲』小学館P.159)に私は全面的に同意しますが、当時は熱心な聴き手ではありませんでした。しかし、いま改めてその頃の天地真理を聴くと、彼女こそ戦後日本が生んだ最初の、しかも最大最強のアイドルであったことが分かります。「白雪姫みたいな心しかない私」とか、「ちょっとこわいの、恋かしら」といった歌を真理ちゃんほど説得力をもって歌うことができた歌手はほかにいないからです。 ◇荒井由実(松任谷由実)が本格的にデビューしたのは1973年11月ですが、当時の彼女は天地真理のような強力な社会的影響力はもっておりませんでした。だいたいユーミンは天地真理の周囲にいたような男子応援団、おやじ応援団をもったことがありません。しかしユーミンは真理ちゃんが強引にこじ開けた新時代の感覚を深めて行きました。それが80年代におけるユーミンの破竹の進撃につながって行くわけですが、そのことは『ダ・ディ・ダ』(1985)以下のアルバムを聴かれるとお分かりいただけるでしょう。 ◇次はサザンオールスターズですが、彼らがデビューしたのは1978年です。彼らは天地真理やユーミンのように「虚構の時代」に積極的にコミットしたわけではないようです。むしろ60年代後半のグループ・サウンズなどよりずっとリアルなイメージを導入しようという志向さえ見られました。そういう志向が大澤真幸の言うところの「虚構の時代」の次の「不可能性の時代」においても、彼らが失速しなかった要因と言えるかもしれません。しかし彼らの音楽はずば抜けてキャッチーでした。『10ナンバーズ・からっと』以下すべて必携です。 ◇日本のポップスはほかにもいろいろありますが、演歌/歌謡曲に移ります。まず藤圭子から行きますが、彼女が「新宿の女」でデビューしたのは1969年でした。彼女のアルバムは70年代初頭において他を圧して売れまくったわけですが、彼女を「虚構の時代」の代表と呼ぶのは無理があるでしょう。藤圭子の登場とほとんど同時にその歌を指示するものとして演歌という言葉が生まれましたが、ということはやはり彼女の歌も新しかったのです。構成された土着的的怨みぶしとでも言いますか。とにかく圧倒的な歌たちでした。 ◇藤圭子の後継者は歌のスタイルで言えば門倉有希でしょう。94年のデビュー曲「鴎・・・カモメ」は、あるいは「不可能性の時代」の到来を告げる歌と言えるかもしれません。驚嘆すべき必殺のうなり、そしてすべてのハード・ロッカーも青ざめる鋼のような声。まだ聴いておられない方はこの機会にぜひ。門倉有希が登場した7年前、1987年に「祝い酒」でデビューしたのが当代最大最高の演歌歌手、坂本冬美です。今回の目録にあるのはオリジナル・アルバムですが、ベスト盤等をお求めの方は「演歌/歌謡曲中古CD目録」からどうぞ。 ◇ところで今回の演歌/歌謡曲中古CDには戦前昭和の歌を収めたアルバムが11点あります。李香蘭(山口淑子)をはじめ、暁テル子、二村定一、徳山たまき、小畑実、藤山一郎、東海林太郎、岡晴夫、灰田勝彦、それに『アジアン・コネクション』に入っている歌たちです。これらのチャーミングでキラーな歌をぜひ聴いていただきたいものです。どれか1枚と言われれば、初期の李香蘭の歌を収めた『私の鶯』でしょう。なんとも魅惑的なソプラノです。曲を提供しているのは、古賀政男、服部良一、そして中国の作曲家たちです。 ◇昭和30年代の歌を、ということでしたら、春日八郎、三橋美智也、三波春男、田端義夫、そして昭和30年代後期になりますが、水前寺清子の2枚組ベストもあります。「涙を抱いた渡り鳥」、「いっぽんどっこの歌」、「三百六十五歩のマーチ」等々。ちょっと変わったアルバムとして、美空ひばりが山田耕作の歌曲を歌ったものがあります。彼女は山田耕作のレッスンを受けていますから、その解釈はある意味では決定版と言えます。「からたちの花」、「この道」、「待ちぼうけ」、「ペイチカ」、「赤とんぼ」、「砂山」等々。  ◇最後がその他邦楽中古CDにリストした『軍歌戦時歌謡大全集』の10点です。これはよくある戦後録音のコレクションとは違って、ほとんどが戦前戦中の録音で、戦時歌謡等はオリジナル録音が中心になっていますから、その時代に特有の気分、情感を味わうことができます。総じて戦意高揚の歌が多いことは言うまでもありませんが、「兵隊ソング」には兵隊たちの自嘲的な歌が少なからず収められています。戦時気分の資料として聴くこともできますし、日本近代史に関心がおありの方は必聴必携と言えそうです。歌っているのは、軍楽隊や合唱団を別にすると、松原操(ミス・コロムビア)、渡辺はま子、高峰三枝子、音丸、豆千代、二葉あき子、菊池章子、藤山一郎、霧島昇、伊藤久男、近江俊郎などです。 ◇最後がその他邦楽中古CDにリストした『軍歌戦時歌謡大全集』の10点です。これはよくある戦後録音のコレクションとは違って、ほとんどが戦前戦中の録音で、戦時歌謡等はオリジナル録音が中心になっていますから、その時代に特有の気分、情感を味わうことができます。総じて戦意高揚の歌が多いことは言うまでもありませんが、「兵隊ソング」には兵隊たちの自嘲的な歌が少なからず収められています。戦時気分の資料として聴くこともできますし、日本近代史に関心がおありの方は必聴必携と言えそうです。歌っているのは、軍楽隊や合唱団を別にすると、松原操(ミス・コロムビア)、渡辺はま子、高峰三枝子、音丸、豆千代、二葉あき子、菊池章子、藤山一郎、霧島昇、伊藤久男、近江俊郎などです。◇ほかにもいろいろあります。とっくりご閲覧ください。尚、大澤真幸の時代区分については改めて検討してみたいと思います。 |
| 新着ガイド〔今週のおすすめ/番外〕 |
◇セロニアス・モンク、バド・パウエル、ペギー・リー、等々 (2008/05/02)  ◇ジャズの中古CD全92点が新着なりました。今回は歴史的名盤の嵐といっても過言ではありません。従って、ここで改めてコメントなど記してもあまり意味がないかもしれません。しかし、これまであまりジャズのCDを買っておられないクラシック・ファン、ポップス/ロック・ファン、邦楽ファン、J-POPファンの皆様にも是非ジャズを聴いていただきたい。そういう方向から少しコメントさせていただきたいと思ったのです。 ◇ジャズの中古CD全92点が新着なりました。今回は歴史的名盤の嵐といっても過言ではありません。従って、ここで改めてコメントなど記してもあまり意味がないかもしれません。しかし、これまであまりジャズのCDを買っておられないクラシック・ファン、ポップス/ロック・ファン、邦楽ファン、J-POPファンの皆様にも是非ジャズを聴いていただきたい。そういう方向から少しコメントさせていただきたいと思ったのです。◇アイテム数は全部で3点しかありませんが、セロニアス・モンクからいきます。3点とも歴史的名盤ですから。なかでもいちばん有名なのが56年に録音された「ブリリアント・コーナーズ」でしょう。共演しているのが、ソニー・ロリンズ(ts)、ポール・チェンバーズ(b)、マックス・ローチ(ds)等ですから、悪かろうはずはずはないのですが、本当の名演が生まれる瞬間がここに刻まれています。大西順子(p)の演奏を聴くと、彼女がいかにモンクのこの奇跡の瞬間を追っていたかがよく分かります。 ◇モンクの音楽はクラシックでいうとバルトークのような感じがします。ですから最初から耳に心地よいわけではありませんが、バルトークの「弦チェレ」や「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」をいい演奏で聴いたら確実にハマる。そういうところがモンクにもあります。「ブリリアント・コーナーズ」と並んで「モンクス・ミュージック」も名盤の誉れ高いアルバムですが、ジャケットは「セロニアス・モンク」(Prestige)を載せました。これは編成の小さいピアノ・トリオですから、モンク入門にもぴったりと思われたからです。ドラムスもアート・ブレイキーとマックス・ローチを聴き比べることができますし、勢いということではこっちの方が上かもしれません。 ◇モンクは3点しかありませんが、バド・パウエルは7点あります。バド・パウエルはジャズが生んだ最大最高のピアニストです。まあラフマニノフとホロヴィッツとグレン・グールドを足して3で割ったようなピアニスト、と言ってもいいかもしれません。アート・テイタム(p)がトスカニーニか誰かを驚倒させたという逸話が残っていますが、トスカニーニ(?)がバド・パウエルを聴いたらなんと言ったでしょう。とにかくこれも20世紀の奇跡のひとつです。「アメイジング・バド・パウエル」の1と2、それに「スティット、パウエル、J.J.」を聴けばお分かりいただけるはずです。しかしバド・パウエルの偉大さは指がまわらなくなった中期、晩年においても音楽が常に高貴であり続けたことにあります。そういう意味ではバド・パウエルのアルバムはすべて必聴です。 ◇バド・パウエル以後のジャズ・ピアニストは、ほぼ例外なくパウエルズ・チルドレンと言えます。その筆頭はハンプトン・ホーズかもしれません。「ザ・トリオ」の2と3がありますが、どちらも必聴です。パウエルの高貴さを受け継いだという意味では秋吉敏子を挙げるべきでしょう。3点あるなかでは、56年の「トシコ・トリオ」がベストかもしれません。バックはポール・チェンバース(b)とエド・シグペン(ds)ですし。ほかの2点も傑作です。「トリオ&カルテット」も、後年の「フィネス」も。パウエル派ではあとウィントン・ケリー、ソニー・クラーク、バリー・ハリス、レイ・ブライアントなどがあります。「ケリー・アット・ミッドナイト」、「ソニー・クラーク・トリオ」、それに「ゴールデン・イヤリングス」が聴ける「レイ・ブライアント・トリオ」はどれも名盤の誉れ高いアルバムです。 ◇ピアニストのものでは、ほかにオスカー・ピーターソン3点、エロール・ガーナー1点、ナット・キング・コール2点があります。パウエル派とは一味違う彼らのピアノもいいのです。とりわけエロール・ガーナーのワン・アンド・オンリーの魅力を収めた「コンサート・バイ・ザ・シー」は一度聴いたら病みつき間違いなしです。ナット・キング・コールのピアノは「粋」という言葉がいちばん適切でしょう。弾き語りの歌も絶品です。バド・パウエルとアート・テイタムを合わせたような豪快なオスカー・ピーターソンもお忘れなく。ピアニストのリーダー・アルバムでは「ホレス・シルヴァー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ」がありますが、これも名盤です。 ◇ホーン奏者以下は駆け足で紹介させていただきます。まず村上春樹が大好きなスタン・ゲッツ(ts)。49年と50年の「カルテッツ」、50年の「ルースト・セッションVol.1」以下5点ですが、どれを聴いてもゲッツの天才ぶりが分かります。アート・ペッパー(as)の5点、リー・コニッツ(as)の5点も、白人奏者ならではの繊細さと鋭さが詰まっています。ソニー・ロリンズ(ts)の6点、コルトレーン(ts)の3点、ジャッキー・マクリーン(as)の5点、マイルス・デイビス(tp)の6点など、いずれも必聴必携盤です。ジョージ・ルイス(cl)、ベッシー・スミス(vo)、キング・オリヴァー(tp)などの古いジャズのCDもありますが、それらを聴くと、モダン・ジャズよりニューオーリンズ・ジャズ、ディキシーランド・ジャズの方が音楽として「深い」ということが見えてくるかもしれません。  ◇純然たるジャズ・ボーカルは4点だけですが、ベニー・グッドマン楽団のバンド・シンガー時代のペギー・リーの歌を収めた「ザ・コンプリート・レコーディングス1941-47」がなんとも言えずチャーミングです。ペギー・リーは20世紀のアメリカを代表する大スター歌手ですが、ジャズ・シンガーとしての彼女は、ビリー・ホリディを強く意識していたようで、アイドル的なところはあまりありません。男たちは彼女の美貌に魅せられていたというところがあります。しかし、グッドマン楽団時代のペギー・リーは声は若いし、歌も可愛らしい。グッドマンのクラリネットもたっぷり聴くことができます。あとのメル・トーメ、クリス・コナー、ダイナ・ショアももちろんおすすめです。 ◇純然たるジャズ・ボーカルは4点だけですが、ベニー・グッドマン楽団のバンド・シンガー時代のペギー・リーの歌を収めた「ザ・コンプリート・レコーディングス1941-47」がなんとも言えずチャーミングです。ペギー・リーは20世紀のアメリカを代表する大スター歌手ですが、ジャズ・シンガーとしての彼女は、ビリー・ホリディを強く意識していたようで、アイドル的なところはあまりありません。男たちは彼女の美貌に魅せられていたというところがあります。しかし、グッドマン楽団時代のペギー・リーは声は若いし、歌も可愛らしい。グッドマンのクラリネットもたっぷり聴くことができます。あとのメル・トーメ、クリス・コナー、ダイナ・ショアももちろんおすすめです。◇ほかにもいろいろあります。ごゆるりとご閲覧ください。 |
| 新着ガイド〔今週のおすすめ/番外〕 |
◇内田光子のモーツァルト、ジョン・ケージ、等々 (2008/05/01)  ◇クラシックの中古CD全76点、それに現代音楽の中古CD全5点が新着なりました。今回も目玉ばっかりてんこ盛りです。従って、なにからご紹介するのがいいか迷ってしまいますが、やっぱり内田光子のモーツァルトからいくのが順当でしょう。「秋の想いは彼女がピカ一」と宇野功芳が賞賛する内田光子のモーツァルト。とりわけ名調律師・辻文明による「ヴェルクマイスター第三法」と言われる古典調律を採用した必殺のピアノ協奏曲全集からいくのが。 ◇クラシックの中古CD全76点、それに現代音楽の中古CD全5点が新着なりました。今回も目玉ばっかりてんこ盛りです。従って、なにからご紹介するのがいいか迷ってしまいますが、やっぱり内田光子のモーツァルトからいくのが順当でしょう。「秋の想いは彼女がピカ一」と宇野功芳が賞賛する内田光子のモーツァルト。とりわけ名調律師・辻文明による「ヴェルクマイスター第三法」と言われる古典調律を採用した必殺のピアノ協奏曲全集からいくのが。◇このモーツァルトのピアノ協奏曲全集は全曲必聴でしょうが、やっぱり「中期」のものが特にいいのではないでしょうか?ケッヘル番号で言うと、K.413、414、415、449、450、451といったところ。とりわけ450に聴かれるロココ的な晴朗さに、内田光子〜ジェフリー・テイト盤の精髄がありそうです。この柔らかさはちょっと比類がありません。古楽器によるインマゼール〜アニマ・エテルナ盤もありますが、これも極上品です。 ◇モーツァルトではあと内田光子のピアノ・ソナタ全集、ピリスの2回目のピアノ・ソナタ全集、リリー・クラウスのステレオによるピアノ・ソナタ全集、シモン・ゴールドベルクとルプーのヴァイオリン・ソナタ集4枚セット、ガーディナーの交響曲3点、トン・コープマンの交響曲集、ハーゲン・カルテットの初期弦楽四重奏曲集、バーバラ・ボニーの歌曲集などがあります。すべて名盤と言って間違いない思います。 ◇モーツァルト以外ではまずシューベルト。アンドラーシュ・シフのピアノ・ソナタ集7枚セット、田部京子の2点、舘野泉の2枚組、フォルテ・ピアノによるオルガ・トヴェルスカヤの2点、トヴェルスカヤがファビオ・ビオンディと組んだヴァイオリン・ソナタ集、ゲルハルト・ヒュッシュ、ロッテ・レーマン、ホッター、そしてベーアによる新旧「冬の旅」4点。シュライヤー、オッター、ファスベンダーの歌曲もあります。 ◇バッハでは、エドウィン・フィッシャーの極めつけ「平均律」から、ビルスマの古楽器による「無伴奏チェロ組曲」はじめ、ピーター・ウィスペルウェイ、長谷川陽子の名盤もあります。ピエール・アンタイの「ゴールドベルク」も聴きものです。ヴィヴァルディはポッジャー、ビオンディ、イル・ジャルディーノ・アルモニコなどがあります。しかし今回特におすすめしたいのもボッケリーニの室内楽6点です。 ◇あとブラームスの室内楽が充実していますし、オイゲン・ヨッフムのブルックナー交響曲全集があるし、アラウのベートーヴェン・ピアノ・ソナタ全集+ピアノ協奏曲全集+トリプル・コンチェルト全14枚セットがあるし、飛び切り音のいいベルグルンドのシベリウス交響曲全集があります。クリストフ・ルセのクープラン2点とラモーも素晴らしいものです。アウネス・バルツァのギリシアの歌もいいし、キャシー・バーベリアンが歌うビートルズ、ワイル、サティ、ストラヴィンスキー、パーセル等々も必聴でしょう。 ◇藍川由美の歌う古関裕而と古賀政男をクラシックにリストしましたが、古関裕而の方は要するに戦時歌謡(いわゆる軍歌)集です。藍川由美さんの強烈な表現主義的歌唱が聴きものです。古賀政男の歌はもう日本のクラシックと言って構わないと思いますが、藍川さんのように「正しく」歌えたら文句なしです。最後が現代音楽ですが、ケージの静けさいっぱいのヴァイオリン音楽、ジョアン・ラ・バーバラのあっと驚くヴォイス、それにマイケル・ナイマンのポップな音楽、いずれもキラーな逸品です。 ◇ほかにもまだいろいろありますが、どうぞごゆるりとご閲覧ください。 |
| 今週のおすすめ〔23〕 |
◇『東京物語』にみる家、規範 (2008/04/24) 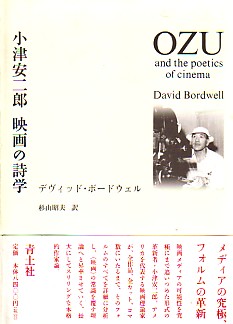 ◇毎度すみません。今回も前回の続きです。蓮實重彦が「私にはまだ充分納得できておりません」(蓮實重彦ほか『国際シンポジウム・小津安二郎』朝日選書P.10)と述べている『東京物語』における老いた父(笠智衆)と義理の娘紀子(原節子)の別れの場面の解読です。 ◇毎度すみません。今回も前回の続きです。蓮實重彦が「私にはまだ充分納得できておりません」(蓮實重彦ほか『国際シンポジウム・小津安二郎』朝日選書P.10)と述べている『東京物語』における老いた父(笠智衆)と義理の娘紀子(原節子)の別れの場面の解読です。◇アメリカを代表する小津研究者であり、映画史、映画理論の大御所でもあるデヴィッド・ボードウェルはこの場面の背景を次のように解説しています。「理想的な「家」制度の下でなら、夫を失った義理の娘は本家に引き取られたものだが、この制度は消滅しており、紀子は他の生き方を見つけなければならない。一生やっていく仕事も持たず、再婚の意思もないまま、彼女はどうしようもなく不安な状態のなかにあることに気づく。」(デヴィッド・ボードウェル『小津安二郎・映画の詩学』青土社P.533) ◇ここでボードウェルが述べている「理想的な「家」制度」とはどういうものでしょうか?その例をわれわれは『小早川家の秋』において原節子が演ずる秋子のあり方に見ることができます。秋子は小早川家の長男と結婚していたのですが、その長男は既に死んでいます。しかし当主にして義父の小早川万兵衛(中村鴈治郎)は、秋子の再婚の世話を焼くことを、なすべき当然の義務、あるいは責任と考えています。 ◇もうひとつ例を挙げると、溝口健二の『お遊さま』のなかで慎之介(堀雄二)の叔母と思われるおすみ(平井岐代子)が語る次のようなセリフがそれに当たります。「・・・(お遊さんの)お亡くなりになったご主人とのあいだには男のお子さんがひとりおいでになるのや。それを育てていかんならんお務めがあるし。・・・女というものは、いったんかたづいたら、先さまのお言葉がないかぎり、帰るわけにはいきませんのや。」 ◇そう言えば『小早川家の秋』の秋子には万兵衛の孫に当たる男の子がおります。しかし『東京物語』の紀子には子供がおりません。そういうことを踏まえてと思われますが、上に引用した部分の少しあとでデヴィッド・ボードウェルは次のように述べています。「彼(義父)は、まるで紀子が家を出ていく未婚の娘であるかのように、彼女にとみ(義母)の形見の時計をやり、事実上の別れを告げる。」(同上) ◇アメリカ人にここまで解説されたら世話はありません。前回述べた「いやあ、ずるうわない」という義父の断定的な、あるいは叱責するような調子というのは、要するにそういうことのようです。つまり、義父の「いやあ、ずるうわない」という言葉と調子は、『晩春』の父が京都の宿で娘の紀子に向かって言う説得の言葉の反復のようなものと考えられるわけです。ボードウェル自身、上の引用の少し前のところで次のように述べています。「『晩春』の曾宮が娘に向かって、自分といっしょに過ごすことで人生を無駄にするなと説得するように、周吉は紀子に、再婚に良心のとがめを感じることはないと言う。」(同上) ◇しかし、そうした義父の心遣いにもかかわらず、『東京物語』の紀子が再婚することはないように思われます。それは「予想」というより、むしろわれわれの「願望」と言うべきかもしれませんが。じっさい『東京物語』の紀子を演じた原節子は、われわれの「願望」に応えるかのように、静かに映画界を退いて独身を通しました。それはともかく、『東京物語』の紀子は「正直さ、不安、そして厳しい道徳的規範」(同上)を体現する人物として造形されています。つまり、東京に戻った紀子がその後も寡婦にして下層の労働者という生き方を続けていくに違いないとわれわれが考えるのは、この映画から受け取る感動によっています。 ◇それは『東京物語』がそういう「メッセージ」を発しているということではありません。「メッセージ」を発しているとすれば、それは「占領色の濃い小津のリベラリズム」(同上)とボードウェルが呼んでいるものを言葉で語っている義父の方でしょう。しかしこの映画の感動は、紀子が体現している伝統的な道徳的規範の方からやってくるようです。要するに『東京物語』は単純な映画ではないということですが、紀子の優しさと強さが彼女自身の道徳的規範からきているかぎり、われわれは紀子の側に立ちたくなります。つまりは古い道徳的規範の側に。映画のなかで義父が「やっぱりあんたはええ人じゃよ。正直で」と語っているように。 ◇『東京物語』のこの場面は、妻に先立たれた老父とその義理の娘である未亡人紀子の対話というにとどまらず、この映画全体の「層」が一挙に輻輳しているようですから、蓮實重彦ならずとも「充分納得」することは至難です。もっと言えば、それまでの小津映画全体とは言わないまでも、少なくとも『一人息子』や『戸田家の兄妹』、そして『晩春』と『麦秋』の諸テーマがここで振り返られているようにも思えます。従って結論のように言うことは控えなくてはなりませんが、『東京物語』はあるべき規範または正義を描いた映画ということはできそうです。そういう意味でヒーロー映画的な傾きをもった映画であるということはできるでしょう。 ◇それにしても不思議な映画です。なにが不思議かといって、過去の遺制のように見做されている伝統的な家制度だとか、そういうものが生み出した道徳的規範があるべき正義として描かれていることがです。しかし『東京物語』を純日本的な映画であるとか、封建主義的な映画であるとか、反動的な映画であるとか言う人はまずいないでしょう。なぜなら、人間社会の約束にせよ合意にせよ、それらを基礎づけるのは紀子が体現しているような規範にほかならないからです。そういういわば普遍的なものを描いた映画だからです。 ◇小津は死ぬ少し前、見舞いにきた松竹大船撮影所長の城戸四郎に向かって「やっぱり映画はホームドラマだ」と語ったそうですが、それは小津のテーマが家と規範にあったことの証しのように思われます。つまり小津は日本の家制度に見られる伝統的なものは自由と解放の桎梏であるだけではないと考えていたということです。これは家を家政にかかわる「オイコス」の領域とし、政治的領域の対極にあるとしたハンナ・アーレントとは正反対の考え方のように見えますが、そうではないと思います。『東京物語』の紀子がそうであるように、家制度は規範を生み出します。愛と連帯も生み出します。もっと言えば、責任と決定も生み出します。 ◇もちろん日本の家といっても、本質的には必要と労働の領域であり、支配と服従の領域であり、結局のところ私的領域であることはアーレントが述べている通りでしょう。しかし物事には両面があります。必要と労働は規範を生み出しますし、支配と服従は正義と抵抗を生み出します。私的であることは人間が公的でありうることを教えます。「映画はホームドラマだ」という小津の言葉はそのように受け取ることができそうです。つまり規範、正義、抵抗を称揚する日本的ヒーロー映画はホームドラマから生まれると。小津や溝口の映画において、女たちがヒロインというよりヒーローのように見えるのは、そのことにかかわっているように思われます。 ◇また、藤純子の『緋牡丹博徒』シリーズのような、ヒロインというよりヒーローと呼ぶべき女主人公を生み出したのは、小津的な映画観からくるひとつの帰結かもしれません。シガニー・ウィーバーの『エイリアン』シリーズとは違って、フェミニズム理論とはまったく縁がなさそう見える『緋牡丹博徒』シリーズを分析してみることで、溝口映画のアヤ子、ふみ、お徳、そして紀子三部作の紀子に代表されるようなヒーロー的女主人公を生み出した日本映画の文化的社会的背景が見えてくるかもしれません。それが日本の文化的社会的文脈からくるのか、それとも映画に固有の文脈からくるのかは、まだよく分からないのですが。いずれにしても、最良の日本映画が達成した次元は、欧米のそれとは微妙に、しかし決定的に違っているようです。 |
| 今週のおすすめ〔22〕 |
◇中野翠の本『小津ごのみ』(2) (2008/04/16) ◇今回は前回の続きです。従来の小津本とは一味違うこの本の新機軸については、前回いちおう押えたつもりですが、なにしろ対象になっているのが小津映画ですから、一回で言い尽くすことはできませんでした。というわけで、今回は中野翠の本『小津ごのみ』(筑摩書房)の二回目です。 ◇この本は作品解説から成る第4章を別にすると、全部で25本のエッセイで構成されています。中野翠という人は役柄とそれを演ずる俳優に関心の中心があるようで、第1章「ファッション、インテリア」を除くと、あとはほとんど役柄とその俳優についての考察に重点がおかれています。そしてそのタイトルを見ていくと、「紀子のくすぐったさ」、「紀子の苦さ」、「小津と成瀬の原節子」、「いわゆる「原節子節」」という具合で、中野翠の関心の中心が紀子と紀子を演ずる原節子にあることは明らかです。もちろんそれでいいのです。「紀子三部作」こそ小津映画全体の核心に位置することは誰も否定しないでしょうから。 ◇前回は『麦秋』に即して中野翠の小津映画の見方を私なりに敷衍してみたわけですが、今回は『東京物語』に即して見ていきたいと思います。ところで蓮實重彦は『国際シンポジウム・小津安二郎』(朝日選書)のなかで次のように述べています。「(『東京物語』の尾道における紀子と義父の名高い別れのシーンの)小津の演出が、私にはまだ充分納得できておりません。父親は心から礼の言葉を述べ、「あんたはええ人じゃよ」と言い添えるのですが、そのとき原節子は、絶望というか、憤りというか、自己嫌悪とさえいえそうな「とんでもない」という一言を口にして、老父の笠智衆から顔をそむけて目を伏せる。その瞬間のショットが、私には消化しがたい異物のようなものとして残っております。」(P.10) ◇いかにも蓮實重彦らしい見方という気がします。たしかにその場面の小津の演出については、いろんな人がいろんなことを述べています。その場合、解釈はもっぱら「とんでもない」が言われる少し前の紀子の言葉「あたくし、ずるいんです」をめぐってなされているようです。従って、「とんでもない」に見られる「いわゆる日本女性の奥ゆかしさとはまるで異質の、ある厳しさ」(蓮實、同上P.12)に着目した方が、「批評的文脈」(P.13)の形成という意味でも生産的ではないかと蓮實重彦が考えるのは分かります。しかし、「あたくし、ずるいんです」も「とんでもない」も、「あんたみたいなええ人はない」への拒絶、否定である点では同じです。 ◇この場面には伏線、というか前段があります。それは紀子のアパートに泊まることになった義母(東山千栄子)と紀子の一対一の会話です。それについて中野翠は次のように述べています。 ◇「(会話のあと)二人はそれぞれの布団に入って眠りにつくのだが、紀子の表情が見ものだ。きつい、淋しい顔になって、やがてウッスラと涙ぐむのだ。〔改行〕 とみ(義母)は腹を割って話しているのだが、紀子は腹を割らない。明るく冗談でいなす。精いっぱい演じているのだ。紀子はなぜ演じてしまったのか。この愛すべき姑への思いやりもあったろうし、今の自分を直視したくないという気持もあっただろう。そして、たぶん、直感的に「この人には私の不幸は分かってもらえない」と察したからだろう。」(『小津ごのみ』P.99-100) ◇紀子が自分を「不幸」と思っているかどうかは分かりません。それは中野翠の想像にすぎないような気もします。しかし、「不幸」ということを別にすれば、「じゃ、おやすみなさい」と言って電灯を消すために立ち上がる前後の紀子の表情に、この「愛すべき姑」には自分のことは分からないという紀子の意識を読むことは、その場面の小津の演出に適った見方であると言えるはずです。 ◇前々回の「小津安二郎の『麦秋』の紀子について」で述べたように、『麦秋』の紀子にそれまでの映画の流れとは異質のものが出現するのは紀子が謙吉と会話をするニコライ堂が見える喫茶店の場面です。また、そこでも言及したように、『晩春』の紀子に「憤り」が噴き出すのは叔母(杉村春子)から父の再婚話を聞いた直後です。いずれの場合においても、それまでとは異質のものが現われる場は"紀子の顔"です。ですから、中野翠がそうしているように『東京物語』の"紀子の表情"に注目することには権利があるのです。 ◇そのような観点からとは言えないでしょうが、中野翠は『東京物語』の義父との別れの場面における紀子の「あたくし、ずるいんです」について次のように述べています。 ◇「紀子は老夫婦をしんそこ愛している。まごころで接している。けれど聡明な紀子は自分の心のトリックーーかすかな偽善にも気がついている。けなげな嫁、感心な未亡人として老夫婦に尽くすことで、今の自分から逃げることを楽しんでいるのではないか、あの大きな悲劇(戦争)が今や日常の中に呑み込まれていっているのを認めるのがおそろしくて、ことさらに老夫婦に縋りついているのではないか・・・・・と。〔改行〕 紀子の「あたくし、狡いんです」という言葉を、私はそんなふうに受け止めた。」(同上P.90) ◇紀子が「今の自分から逃げることを楽しんでいる」かどうかは分かりません。しかし「聡明な紀子は自分の心のトリックーーかすかな偽善にも気がついている」というのは、実に鋭い指摘と言えます。その場面から読み取れることは、紀子が宙ぶらりんの状態、あるいは分裂した状態にあるということでしょうから。具体的に言えば、亡夫昌二へ未亡人としての思慕と、それが失われてきている現実とのあいだで不安な状態にあるということ。紀子の言葉「あたくし、ずるいんです」がそのことを指していることは疑えないと思います。 ◇従って、紀子の「ずるいんです」に対する義父の言葉、「いやあ、ずるうわない」、「ええんじゃよ、それで。やっぱりあんたはええ人じゃよ、正直で」は、会話としてはかみ合っています。かみ合っていないのは、紀子の不思議な表情です。その前の「お母さま、あたくしを買いかぶってらしったんですわ」から現われてくる紀子の表情には冷やかな笑いのようなものが見られます。あるいは「ずるい女」、「悪い女」を表情にするとこうなるという、そういう挑発的、挑戦的な表情にも見えます。一体これは何なのでしょうか? ◇たぶんそれは「戦後日本人の顔」なんだろうと思います。小津は「戦後日本人の自画像」のようなものを画面に刻みつけようようとしたのではないかと思うのです。あるいは、小津の意図を超えて原節子がそういう顔を演じたということも考えられます。そうであるにしても、小津はそれをよしとしたのでしょう(実を言うと、紀子の冷やかさは、義母との一対一の会話場面にもその片鱗が見られます)。 ◇それは笠智衆演ずる義父に向けられた顔でもあるわけですが、明治16年頃の生まれと思われるこの映画の義父はそういう紀子の「正直」さを受け入れます。戦後の日本人は普通はそういう「ずるさ」や「悪さ」を紀子のようには見せないからだと思われます。「いやあ、ずるうわない」という義父の断定的な、あるいは叱責するような調子には、そういう受け止め方が感じられます。義父が叱責しているとすれば、露悪的なほど厳格な紀子の倫理感に対してです。そこまで自分を責めることはない、ということです。 ◇この場面における義父の言葉とスタンスについては更に「深い」読みが可能かと思いますが、こうして物語は死んだ義母が残した懐中時計の形見分けへと、つまりは義理の老父母との新たな「和解」へとつながっていくわけです。もちろん、そうしたところで紀子の不安や孤独がやわらげられるわけではありません。しかし紀子と死者たち及び義父との絆がより強く深いものになっていることは間違いないようです。東京へ戻った紀子はその後も寡婦にして下層の労働者という生き方を続けていくのでしょうが。 ◇とにかく『晩春』の紀子に現われる「憤り」、そして生きている肉親に対する『麦秋』の紀子の「軽侮」を踏まえると、『東京物語』の紀子に「戦後という時代のあるべき、あるいは生(なま)の姿」のようなものを見ることは、それほど突飛なことであるとは思えません。『麦秋』の紀子の「軽侮」は、『東京物語』の紀子にも、「自分自身を含む素朴な善良さへの軽侮」という形で引き継がれているようです。いずれにしても、『東京物語』の紀子が弱い女でも素朴な女でも断じてないこと、これだけははっきり言えます。 ◇以上に述べたことは、蓮實重彦の言い方を借りれば「想像の域を超えるものでは」ない(上掲本P.12)かもしれません。しかし、原節子演ずる紀子について言えば、中野翠がそうしているように、ヒロインの表情に着目することには権利がある。そう言って構わないはずです。もっと積極的に言えば、紀子を演ずる原節子の表情には、時代の底に隠されているものを引きずり出すような力さえあるようです。 ◇従って、「小津安二郎作品中の原節子は、いまや世界が共有する伝説となった」(関川夏央『女優男優』双葉社P.46)と言われるのはもっともなことです。むかし「女優は二人しかいない」と言われたそうですが(原節子と高峰秀子の二人)、「ディーバ(女神)は一人しかいない」、そうも言いたくなります。『二十四の瞳』(木下恵介)や『稲妻』(成瀬巳喜男)でヒロインを演じた高峰秀子ももちろん素晴らしいのですが。 |
| 今週のおすすめ〔21〕 |
◇中野翠の本『小津ごのみ』 (2008/04/10)  ◇今回のおすすめはひさしぶりに本で行きます。とは言いましても、小津映画についての本です。また、この本は今年になってから出たもので、当店にはまだ在庫がありません。ご了承ください。ちなみにこの本の発行日は2008年2月25日で、出版社は筑摩書房です。 ◇今回のおすすめはひさしぶりに本で行きます。とは言いましても、小津映画についての本です。また、この本は今年になってから出たもので、当店にはまだ在庫がありません。ご了承ください。ちなみにこの本の発行日は2008年2月25日で、出版社は筑摩書房です。◇中野翠(みどり)の本を読んだのはこれが初めてですが、力のある書き手がいるもんだなあと思いました。例えば次のような一節。 ◇「原節子に限らず小津映画の人びとの会話のリズムや間からは、何か独特の不自然さも感じた。限りなく自然を装ったような不自然さ。それは登場人物のセリフ術ばかりではなく、仕草や動作にも感じられた。ヘンじゃないの、滑稽じゃないのと思っているうちに、それが妙に快くなってしまう。馴らされてしまうのだ。」(P.173) ◇まったくその通りです。われわれは映画をみることを通じて、映画的リアリティに慣らされていくのですが、小津の映画においてはそれが特に誇張されているように感じられる。だから小津の映画はヘンな映画だ、異様な映画だと言われるのでしょうが、われわれが映画にリアリティを感じること自体がヘンなこと、異様なことであるとも言えます。 ◇しかし映画はそういう風に成り立っています。例えば『麦秋』終盤のアヤの部屋の場面で、アヤ(淡島千景)と紀子(原節子)が秋田言葉でしゃべり合ったあと、話題が謙吉(二本柳寛)のことに移るところでアヤが立ち上がって少し歩く。そして思い出したように振り返って紀子に聞きます。「ねえ、ほら、いつかお宅の省二さんまだスマトラへ行く前、みんなで城ヶ島へ行ったことあったでしょ。あの時の人?」。これが小津映画に見られる"転調"のやり方です。たしかにヘンと言えばヘン、異様と言えば異様なのですが、このアヤの動作がなければ、「お宅の省二さん」「スマトラ」「城ヶ島」という言葉は特別な響きをもちえなかったでしょう。 ◇上に引用した文章で中野翠が言っているのはもっと一般的なことかとも思われますが、アヤが紀子たちの鎌倉の家にやってくる場面では、学校時分仲がよかったふたりの友達(マリと高子)がこられなくなったことを知った紀子はがっかりして、「ああ、そう」を最初に1回、あとで2回繰り返します。同じフレーズが繰り返されることで、みる者は紀子の気分に身体が同調していきます。感情というより身体が。 ◇そのあと紀子とアヤがテーブルに向かって並んで座り、同じ方向を向いて同じような動作を繰り返します。こうした動作の相似形は小津が得意とした演出ですが、これは効果としては音楽におけるポリフォニーやフーガに相似的と言えるでしょう。小津が西洋のルネサンス音楽やバロック音楽を好んだかどうかは知りませんが(たぶんそういう事実はなかったと思いますが)、小津のつくった映画が結果としてバッハの「無伴奏チェロ組曲」や「無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ」などに通ずるような効果をもつことになったことは否定できないと思います。いずれにしても小津の映画はバッハの音楽のようです。 ◇話が飛びすぎてしまいました。中野翠のこの本は「ドンゴロスと女たちのきもの」という文章で始まりますが、縞、格子、かすりの着物、白いブラウス+無地のスカートという「制服的ファッション」など、これまであまりとり上げられることのなかった小津趣味への着目がとても新鮮です。しかし中野翠の目の鋭さを感じるのは、やっぱり小津映画の異様さにかかわる記述です。次に引く文章もそうです。 ◇「もしかすると、周吉や紀子などの「毎度おなじみ」の役名は、能面の呼称に近いものなんじゃなんいかという気がして来るのだ。・・・(能の面は)大ざっぱに年齢・性別・身分などで分類されているだけで、パーソナリティや感情は演者の動きによって表現される。小津にとっての役柄は個人よりもっと広がりのあるもので、それが役名の繰り返しにも象徴されているように思うのだ。」(P.83) ◇こわいような洞察ですね。能に注目したところがすごいと思います。小津映画のドラマというのは仮面劇のようなものではないかというのは前から感じていたことですが、要するに小津が目指していたのは「型」のドラマなのだと思います。これは小津の映画がバッハの音楽のように思えることにもかかわってきますが、小津が映画において切り取ったのは、個々の人間ドラマというより、むしろ世界そのもの、あるいは宇宙といわれるようなものです。つまり、小津は個々の動作、表情、セリフというものをいかにもリアルに見せるのではなく、むしろそれらが凝縮された「型」へと還元していく。そういう意味で小津の場合、音楽においてシェーンベルク、ブーレーズ、ジョン・ケージがもっていたような方法意識を共有していた可能性があります。 ◇小津は人間の心理というものにはあまり関心がなかったようにも思われますが、それは小津の関心が「型」の方に向けられていたからでしょう。あるいは個々の心理状態より「型」の方が普遍的であるという確信があったからでしょう。言い換えれば、個々の人間心理といったところでそれらは実はたいへん大ざっぱなもので、それらに"深さ"を与えるのはむしろ「型」の方であるという考え方です。小津は正しかったのだと思います。中野翠はこの本の最後の章で次のような小津の言葉を紹介しています。 ◇「感情過多は、ドラマの説明にはなるが、表現にはならない。・・・徒に激しいことがドラマの面白さではなく、ドラマの本質は人格をつくり上げることだと思う。」(P.217) ◇まったくその通りだと思います。例えば映画『麦秋』のドラマは淡々と進行していきますが、終盤の紀子が勤める会社の応接室における紀子と矢部たみ(杉村春子)のやりとりなど、本当は淡々としているとはとても言えないのです。たみ「ねえ、お父さまお母さま、もうご存知かしら?(紀子が、たみの息子謙吉との結婚を承諾したことを)」、紀子「ええ」、たみ「お兄さまも?」、紀子「大丈夫」。 ◇紀子は「大丈夫」と言いますが、兄の康一は前の晩、「お父さんお母さん、なんとおっしゃるか知らんが、おれは不賛成だね」と言っています。それを紀子は「大丈夫」と言う。つまり、紀子は兄康一の意見などほとんど歯牙にもかけていないということを、われわれは知るのです。紀子の言葉の裏にはそういう「激しさ」があるのですが、そのことは紀子の両親を見遣る視線と兄康一を見遣る目の仕草の違い、つまり「型」を通して表現されます。つまり、紀子の両親を見遣る視線には「畏れ」がありますが、兄康一を見遣る視線にあるのは「軽侮」と「警戒」です。このようにして紀子の人格がつくり上げられていくわけです。 ◇ついでだからもう少し言っておきます。上のやりとりに続いて、たみと紀子のあいだで次のような会話が交わされます。紀子「でも、謙吉さん、なんと思ってらっしゃるか」、たみ「誰?謙吉?・・・もう大変。あの子だってゆうべよく寝てやしませんよ。夜中にまた一緒にご飯たべちゃったの」、紀子「そう」。 ◇これが小津の映画です。ご飯をたべるという「型」はここではセリフで語られるだけですが、その少しあとに、夜遅く帰宅した紀子がひとり台所で旺盛にお茶漬けをたべる場面が出てきます。紀子は謙吉との結婚を承諾するに当たって夫になる謙吉をつんぼ桟敷においていたのですが、謙吉とたみが夜中にまたご飯をたべたという報告を通して、われわれは謙吉がそれを受け入れたことを知るのです。 ◇というわけで、この中野翠の『小津ごのみ』は小津映画をみていく上で、いま考えられる最良のガイドブックと言えます。彼女が以前に書いた『会いたかった人、曲者天国』(文春文庫)には小津映画の俳優たち(佐分利信、斎藤達雄、桑野通子)、同輩たち(山中貞雄、清水宏)についてのエッセイが収められています。併せてお読みいただければ、映画への理解がいっそう深まるはずです。 |
| 今週のおすすめ〔20〕〔19〕〔18〕〔17〕〔16〕へ |
トップページへ戻る